刊行物
拠点で刊行している書籍シリーズは、以下の通りです。
法政大学能楽研究所紀要『能楽研究』 1~49
能楽研究叢書1~9
能楽資料叢書1~9
拠点研究活動報告『Journal』1~8
能楽研究叢書1~9
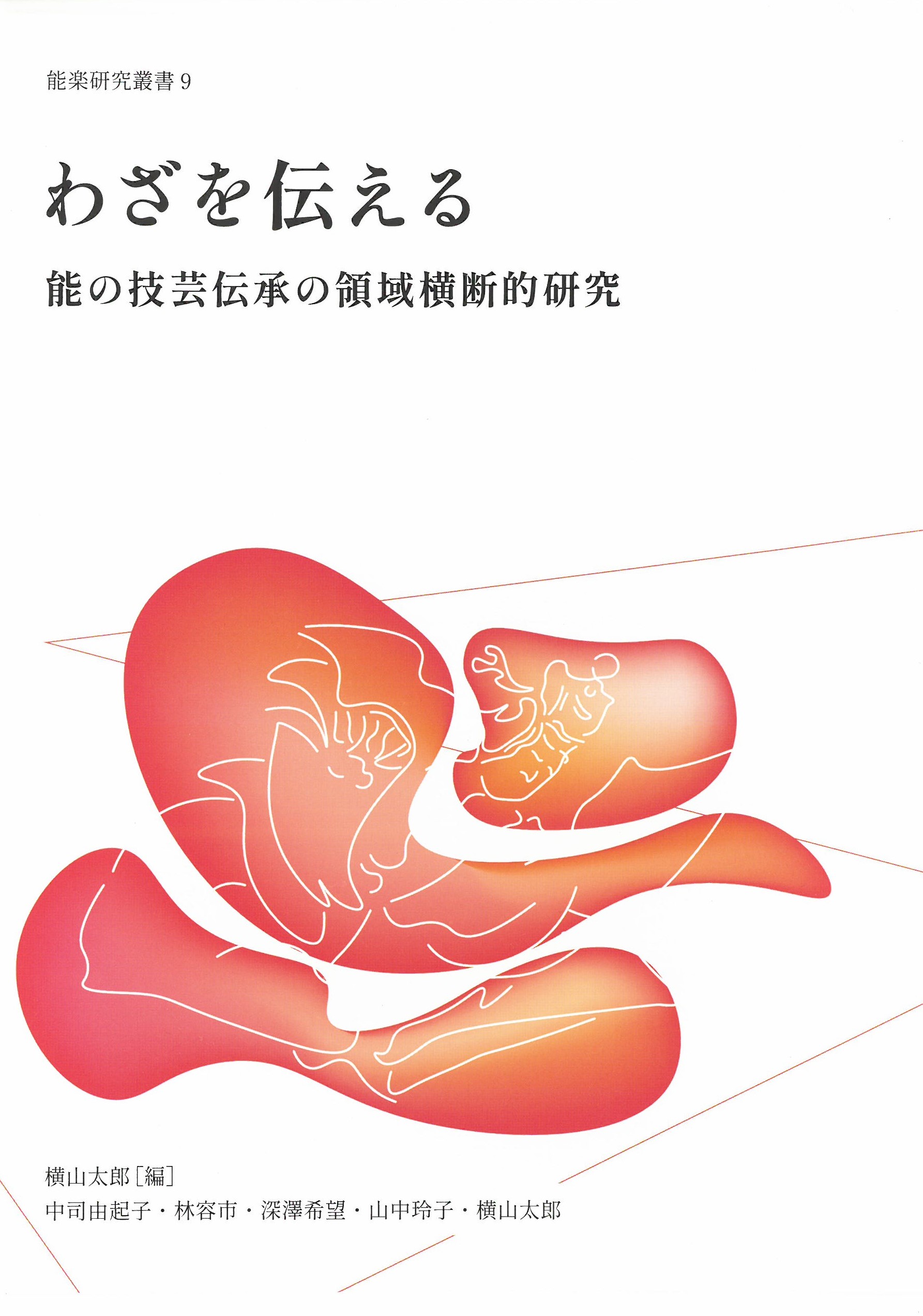 |
能楽研究叢書9『わざを伝える―能の技芸伝承の領域横断的研究』横山太郎編 フィールドワークと歴史研究の両側面から能の技芸伝承に迫ろうとする論文集。公募型共同研究の成果(能楽の技芸伝承・脇型付)。口絵に「能付資料の世界―技芸伝承の軌跡をたどる―」(会期:2018年2月20日~3月24日)の記録を収める。 |
 |
能楽研究叢書8 『危機と能楽』中司由起子・深澤希望・宮本圭造・山中玲子編 能楽研究所創立70周年記念・HOSEIミュージアム特別展『危機と能楽』(会期:2022年9月1日~2023年1月31日)の図録を基礎に、増補改訂版として編集した一冊。 |
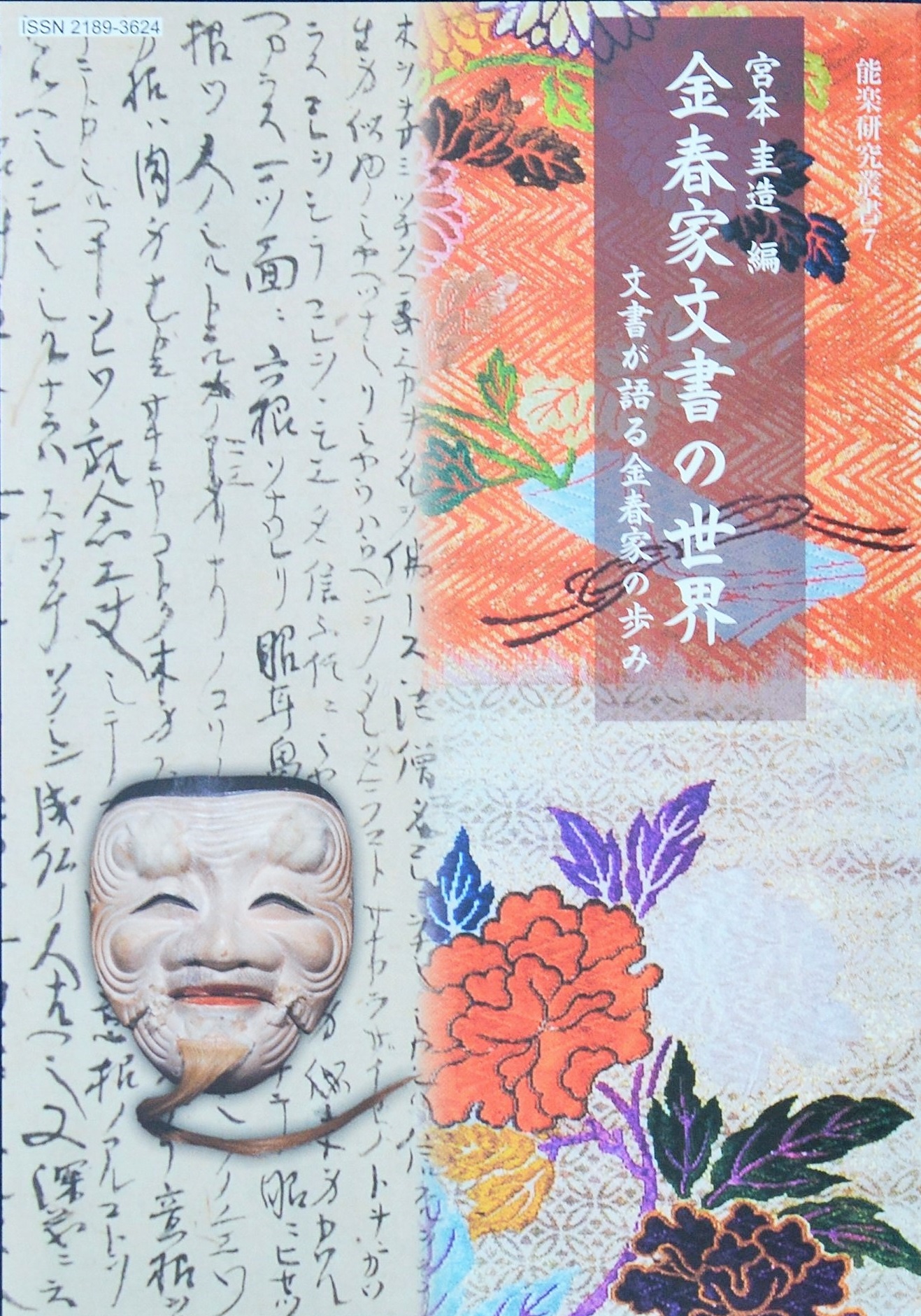 |
能楽研究叢書7 『金春家文書の世界』宮本圭造編 2014年9月15日開催のシンポジウム「金春家文書の世界―文書が語る金春家の歩み―」の報告集。金春安明氏の巻頭言と登壇者の論文を所収する。能楽研究所般若窟文庫、金春家に伝来する文書についての論文集。 |
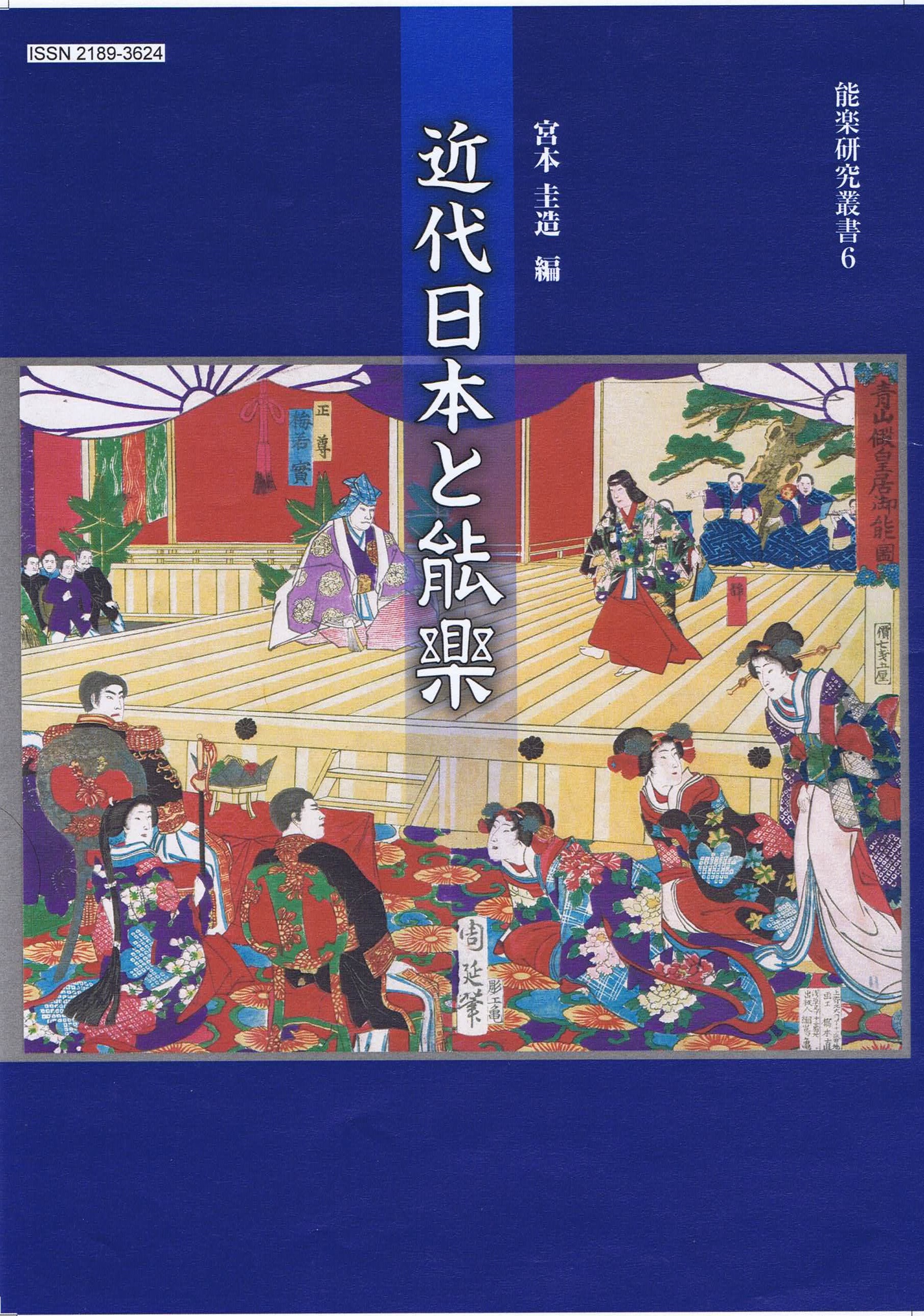 |
能楽研究叢書6 『近代日本と能楽』宮本圭造編 2013年10~11月開催の第17回能楽セミナー「近代日本と能楽」の報告集。基調講演・登壇者の論文・特別寄稿論文を所収する。近代の能楽史を総合的にとらえた一冊。 |
 |
能楽研究叢書5 『能楽の現在と未来』(山中玲子編) 2014年10月~11月に開催した能楽セミナー「能楽の現在と未来」のすべての発表・講演等を活字化。英語能に関する論考・実践報告(英文・2本)、新作狂言や狂言普及活動についての論稿も所収。2006年以降の新作能リストと新作狂言リストも掲載した。 |
 |
能楽研究叢書4 『野上豊一郎の能楽研究』(伊海孝充編) シンポジウム「生誕130 年 野上豊一郎の能楽研究を検証する」(2013 年度開催)の報告集。講演の記録、発表をもとにした論文等と、能楽研究所蔵の野上文庫蔵書目録・野上豊一郎著作目録を収める。 |
 |
能楽研究叢書3 “EXPRESSIONS OF THE INVISIBLE: a comparative study of noh and other theatrical traditions” Edited by Michael Watson and Reiko Yamanaka 2013 年にイギリスのロイヤル・ホロウェイ大学、オクスフォード大学で開催した能の演技についての講演とワークショップ、討論会の英文による報告集。能と京劇の演技を比較する論文や、能の表現方法や演技の特徴などを述べた講演、能とコンテンポラリーダンスの競演の記録等を収める。 |
 |
能楽研究叢書2 『ギリシア悲劇と能における「劇展開」―アリストテレースを手引きに、そして彼を超えて―』 メイ・スメサースト(著)、渡辺浩司・木曽明子(訳) スメサースト氏著の“Dramatic Action in Greek Tragedy and Noh: Reading with and beyond Aristotle”の日本語訳。 |
 |
能楽研究叢書1 “ZEAMI: SIX REVIVED BANGAI PLAYS” ロイヤル・タイラー(訳) 現存する世阿弥自筆能本のうち、番外曲になっているAkoya no matsu・Furu・Hakozaki・Matsura Sayohime・Tadatsu no Saemon・Unohaの英訳。底本はすべて世阿弥自筆能本。 |
能楽資料叢書1~9
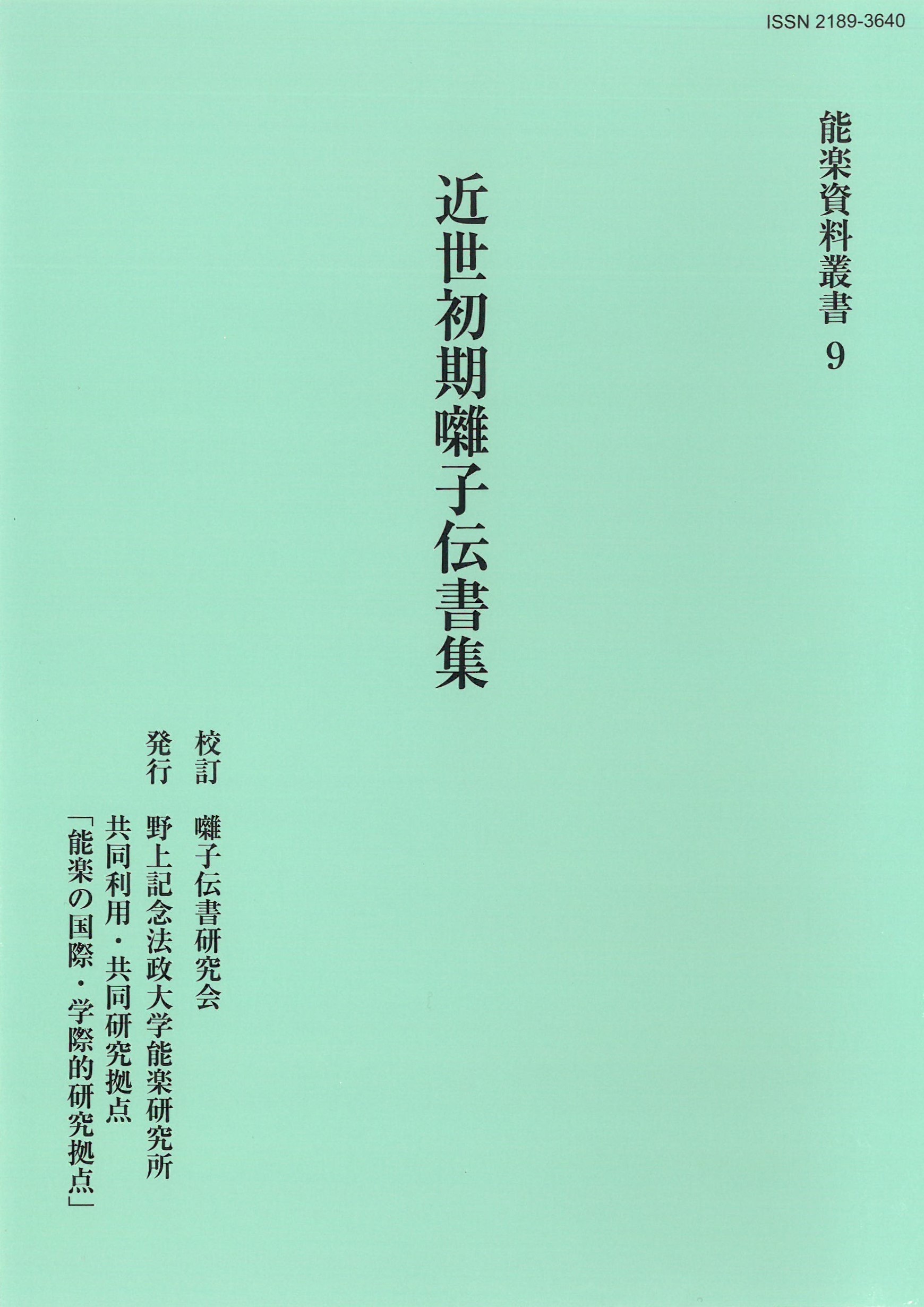 |
能楽資料叢書9『近世初期囃子伝書集』(囃子伝書研究会校訂) 平成25~28年度の拠点主導型共同研究で行った能楽研究所蔵『二見忠隆奥書戦国期囃子伝書』研究会と、平成31~令和6年度の公募型共同研究「一噌流の伝承研究」(研究代表:京都芸術大学准教授 森田都紀氏)の成果を一冊にまとめたもの。『二見忠隆奥書戦国期囃子伝書』と国立能楽堂蔵『笛伝書残簡』、『目録付古頭付』、『いろは順古頭付』、『唱歌残簡』の計5種の翻刻・解説とともに『戦国期囃子伝書』に関する論考、津藩笛方一噌家文書目録を収める。全212頁。 |
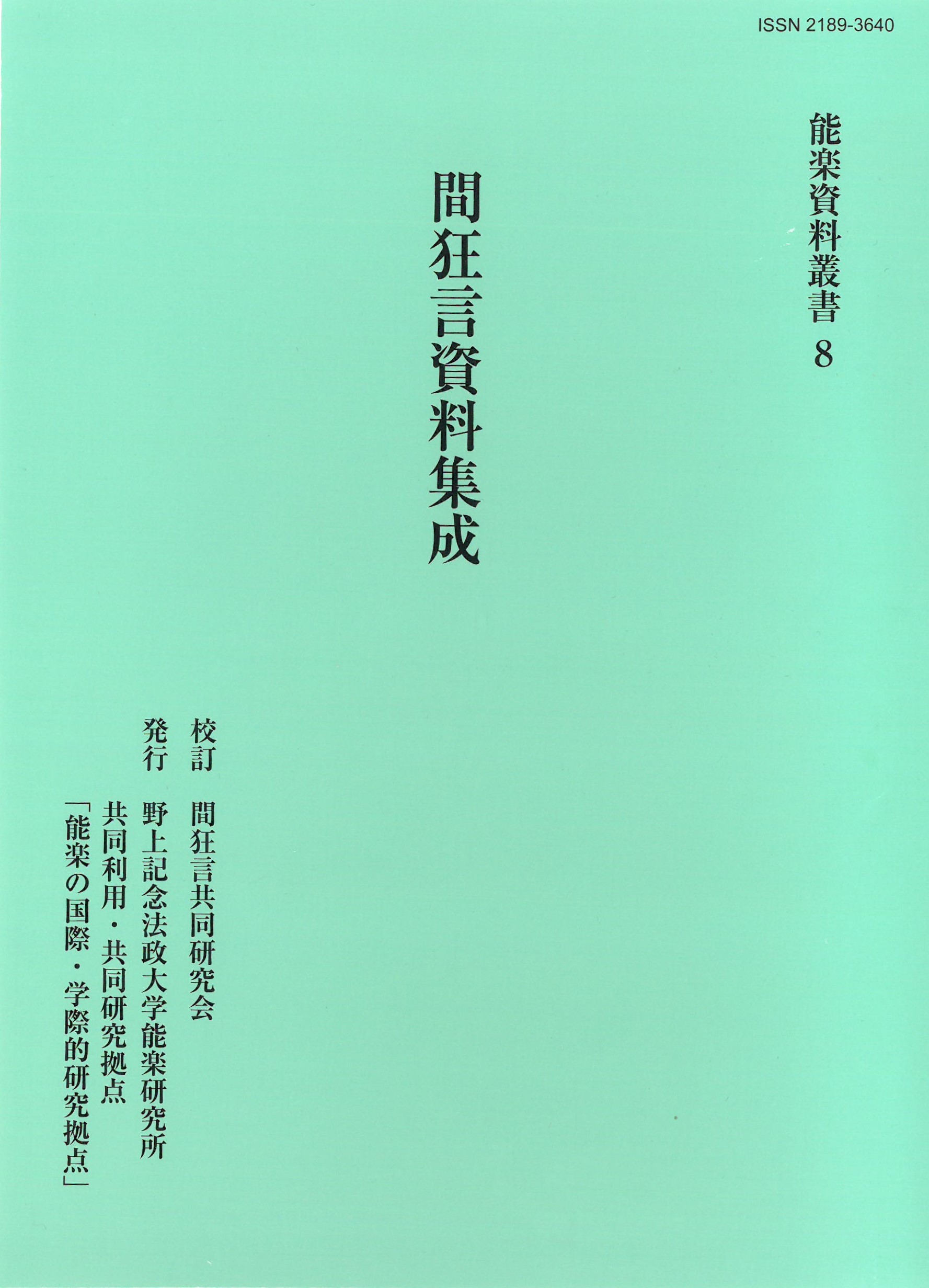 |
能楽資料叢書8『間狂言資料集成』(間狂言共同研究会校訂) 未翻刻資料の多い和泉流・鷺流を中心に間狂言資料を集成。升形本『あい之本』、『鷺流間狂言付』、『鷺流狂言型附遺形書』、『鷺流間の本』、『大蔵流間習分』、『和泉流間狂言伝書』の六種の資料の翻刻・解題・曲名索引を収める。西村聡氏を研究代表とする公募型共同研究の成果。 |
 |
能楽資料叢書7『近世諸藩能役者由緒書集成(下)』(宮本圭造編) 近世諸藩に抱えられていた能役者の経歴を知るには、各能役者から藩に提出された由緒書がまずは最も重要な資料となる。これは言わば履歴書に相当するもので、各人の生没年、職歴などが詳細に記録され、近世の能役者がいかなる身分に所属し、どういった職歴を歩んだかが、由緒書の記述から明らかになる。本書は、これら全国諸藩の能役者由緒書を網羅した初めての企画で、下冊には小倉藩から鹿児島藩にいたる19藩の能役者の記事、(上)の補遺、「近世諸藩能役者分限帳集成」を収める。 |
 |
能楽資料叢書6 『近世諸藩能役者由緒書集成(中)』(宮本圭造編) 全国諸大名57家に仕えていた能役者の由緒書を集成。中冊にはそのうち福井藩から高知藩にたる20家分を収録。能の地方的展開、家元を頂点とする能楽社会の構造の在り方、能役者の社会的身分など、能役者の動向を通して江戸時代の能ついて考察する上で有益な一冊。 |
 |
能楽資料叢書5 『近世諸藩能役者由緒書集成(上)』(宮本圭造編) 全国諸大名五十七家に仕えていた能役者の由緒書を集成。上冊にはそのうち徳川御三家、及び弘前藩から大聖寺藩にたる計18家分を収録。能の地方的展開、家元を頂点とする能楽社会の構造の在り方、能役者の社会的身分など、能役者の動向を通して江戸時代の能ついて考察する上で有益な一冊。 |
 |
能楽資料叢書4 『島根県立図書館蔵 御囃子日記』(小林准士〔島根大学教授〕校訂) 江戸時代に松江城でおこなわれた町人による「御松囃子」の活動記録の翻刻。筆者は松江の商人瀧川伝右衛門。松江藩の能楽史の実態解明につながる資料である。 |
 |
能楽資料叢書3 『東北大学附属図書館蔵 秋田城介型付』(秋田城介型付研究会校訂) 江戸時代初期の能の実態を伝える型付の翻刻。秋田城介が下間少進らから教わった型を書き留めた資料。〈白楽天・定家・船弁慶〉など、38 曲を所収する。 |
 |
能楽資料叢書2 『金春安住集 歌舞後考録・御用留』(六麓会校訂、小林健二編) 金春八左衛門安住の記した『御用留』・『歌舞後考録』(能楽研究所般若窟文庫蔵)の翻刻。前者は天明2 ~ 3 年、安住が江戸城等に出勤した際の覚書や書上などの記録。後者は文政4 ~ 6 年にかけての出勤記録、及びその際の注意事項等を書き留めたもの。 |
 |
能楽資料叢書1 『大蔵虎清 間・風流伝書』(田口和夫校訂) 江戸初期に大蔵虎清がまとめた間狂言・風流の演出に関する伝書(法政大学鴻山文庫)の翻刻。風流15 曲・間狂言223 曲の装束付、囃子等について記したもの。他に虎清に関する資料三篇を付録として収める。 |
拠点研究活動報告『Journal』 1~8
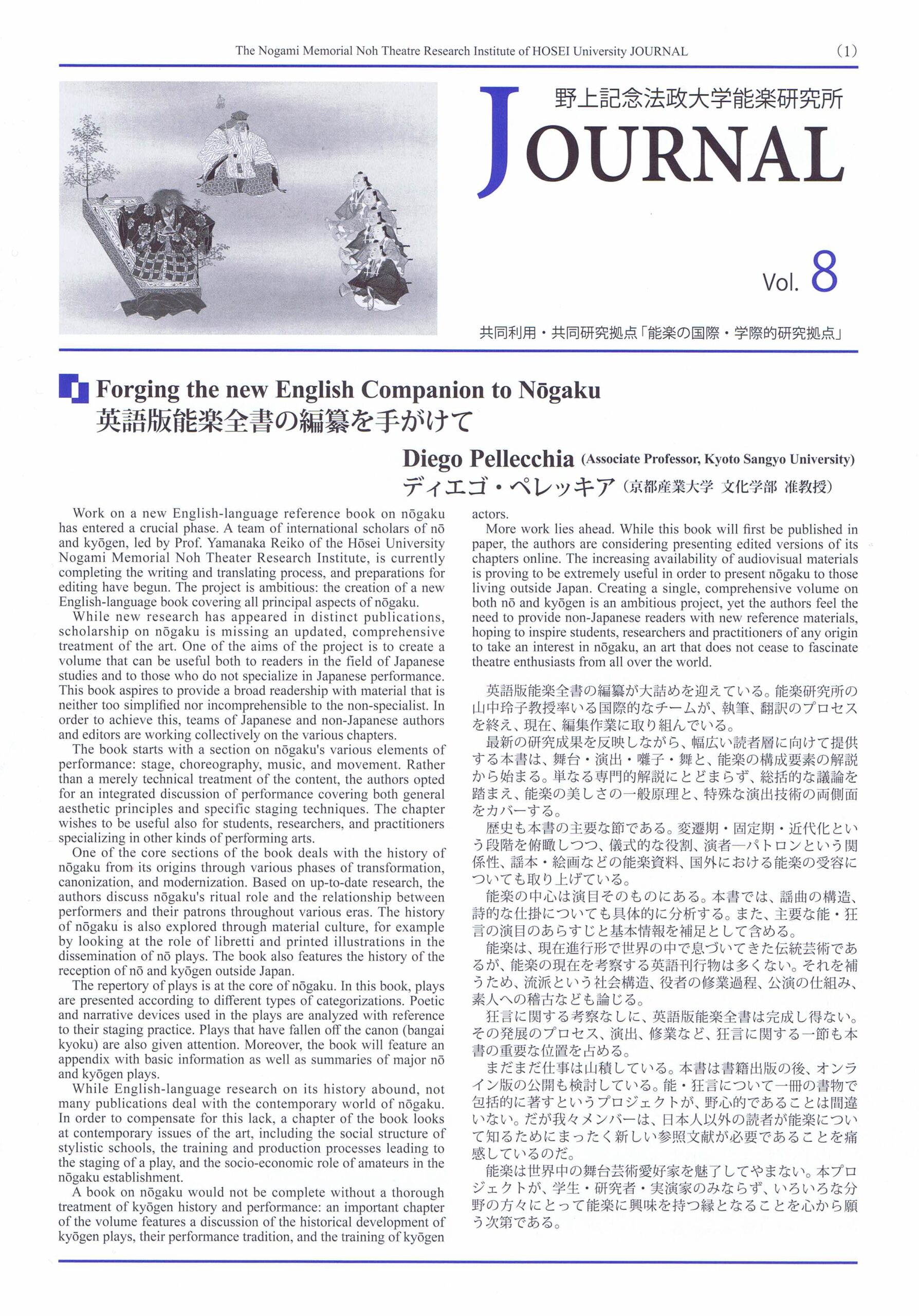 |
拠点研究活動報告 『Journal』第8号 2018年度の活動報告 |
 |
拠点研究活動報告 『Journal』第7号 2017年度の活動報告 |
  |
拠点研究活動報告 『Journal』第6号 2016年度の活動報告 |
 |
拠点研究活動報告 『Journal』第5号 2015年度下半期の活動報告 |
 |
拠点研究活動報告 『Journal』第4号 2015年度上半期の活動報告 |
 |
拠点研究活動報告 『Journal』第3号 2014年度の活動報告 |
 |
拠点研究活動報告 『Journal』第2号 2014年度の活動報告 |
 |
拠点研究活動報告 『Journal』第1号 2013年度の活動報告 |
